試用期間は、社員の能力、適性を図るために、会社にとって重要な制度。解雇権が制限され、正社員とした後だと、辞めさせるハードルはとても高いものです。そのため「まずは契約社員で雇用する」という会社は少なくありません。
しかし、試用期間で雇用するのと、まずは契約社員として雇用するのでは、法的な性質には大きな違いがあり、注意すべき点も多くあります。試用期間は、正社員を前提とするのが原則で、長期雇用だからこそ存在する制度のため、契約社員に適用する際には、慎重に判断する必要があります。
契約社員という雇用形態は、社員としての適性を判断するため、試用期間と同じ意味で活用される例もありますが、たとえ契約社員としての雇用でも、会社の一方的な判断で辞めさせるのには限界があります。契約社員を、更新せずに退職させる、いわゆる雇い止めもまた、解雇と同様に制限されているからです。
今回は、契約社員に試用期間をつけることができるか、有期雇用の試用期間についての注意点を、企業法務に強い弁護士が解説します。
- 契約社員でも試用期間を付けることができるが、妥当な期間に限らなければならない
- 契約社員に試用期間を付けたとしても、辞めさせるにはやむを得ない事由が必要となる
- 試用期間の間は、契約社員として雇う方法でも、結局のところ雇い止めは制限される
\お気軽に問い合わせください/
契約社員に試用期間を付けることができる
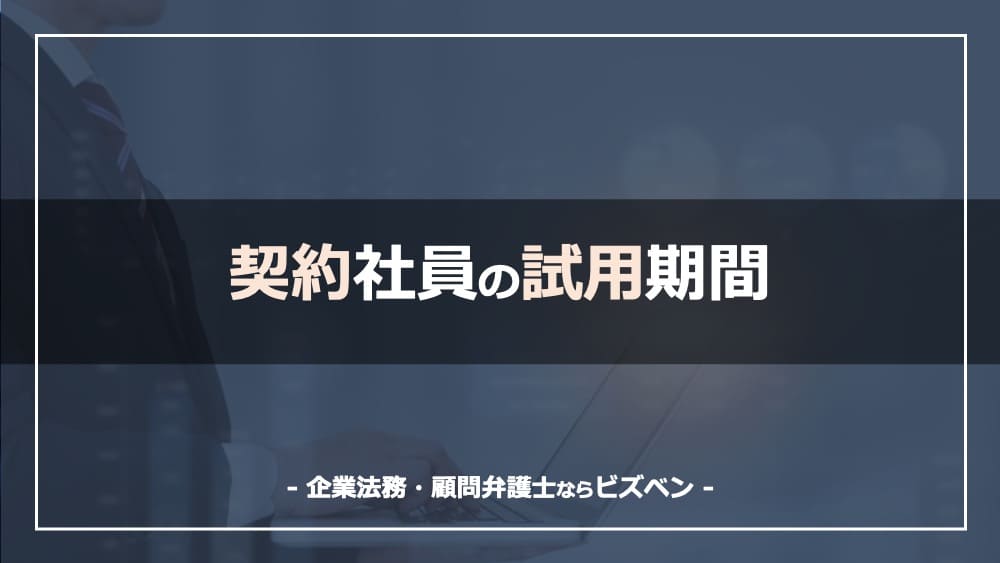
試用期間は、一定の期間のうちに対象者の能力、適性を評価し、社員にふさわしいかを判断し、雇用を継続するかどうかを決定する制度。試用期間における判断の結果、雇用を継続することを「本採用」、雇用を終了して退職させることを「本採用拒否」と呼びます。
試用期間は、長期雇用を想定しているため、正社員に設けられるのが原則です。長く雇用することを保障され、かつ、解雇が制限されているからこそ、雇用の開始時に、試用期間における慎重な判断をする必要があるためです。
とはいえ、冒頭で解説の通り、契約社員でも、試用期間を設けたいニーズはあります。契約社員とて、期間途中の解雇が難しいのは当然、期間満了時の本採用拒否についても会社が一方的に判断できるわけではありません。つまり、有期雇用といえど、契約終了は困難なケースが少なくないのです。
有期雇用は、期間満了により終了するのが原則。しかし、有期雇用が形骸化していたり、労働者に更新継続の期待があったりする場合には、その更新拒絶には正当な理由を要するという「雇い止めの法理」によって保護されるからです。
雇い止めの法理について、詳しくは次の解説をご覧ください。
結論として、たとえ契約社員であっても、試用期間を付けることができます。試用期間は、雇用形態によらずに設けられる制度であり、法律上も、禁止される場面についての定めはありません。有期雇用のうち、契約社員はもちろんのこと、アルバイトやパート、定年退職後の嘱託社員であっても、試用期間を設定することに変わりはありません。
契約社員に試用期間を付ける方法
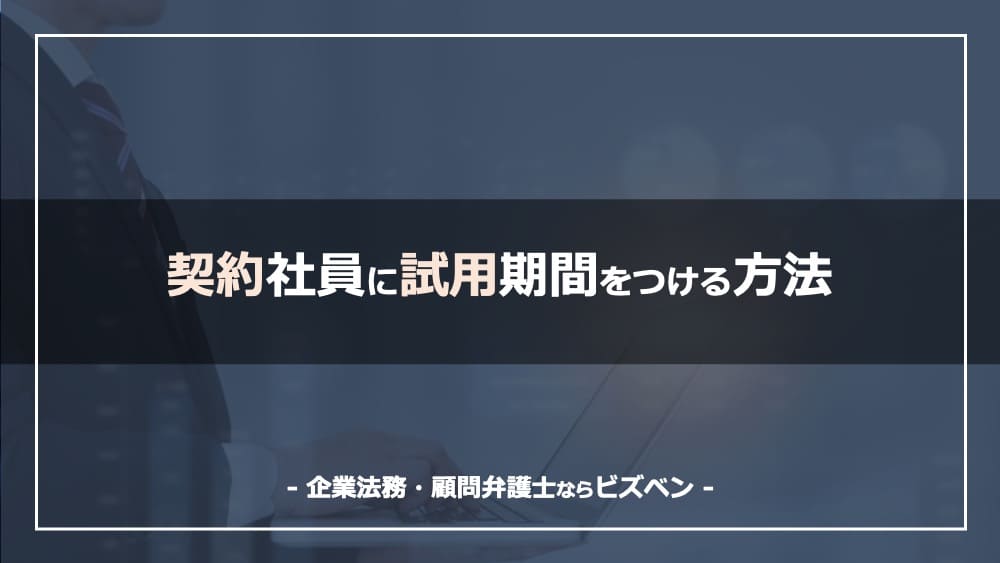
契約期間中の解雇はもちろん、契約期間終了によって更新せずに終了する雇い止めが容易ではありません。このことが、たとえ契約社員でも試用期間を付けるべき、と考える企業が多い理由となっています。
このとき、実際に、契約社員に試用期間を付けるにはどうしたらよいか、その具体的な方法を解説します。
契約社員の試用として適切な期間を検討する
契約社員でも試用期間を付けられるとしても、あまりに長すぎる期間とするのは不適切です。
正社員なら、無期限で雇用されるうち初めの3ヶ月〜6ヶ月を試用期間とするのが通例。これに対し、有期雇用の契約社員の場合、そもそも労働契約期間が数ヶ月〜1年程度に限定され、更新によって継続するのが一般的です。すると、例えば1年間の労働契約期間のうち6ヶ月が試用期間といった設定だと、「契約の半分が試用期間」というイビツな形になってしまいます。
どこからが違法か、明確な基準はないものの、契約社員の試用として、能力、適性を判断するのに適した期間とする必要があり、実務上は、次のような程度の定めをするケースが多いです。
- 3ヶ月未満の契約社員
試用期間1ヶ月未満 - 3ヶ月〜6ヶ月未満の契約社員
試用期間2ヶ月未満 - 1年の契約社員
試用期間3ヶ月未満 - 3年の契約社員
試用期間6ヶ月未満
雇用契約書に記載する
「試用期間をつけるかどうか」は、労働契約の内容となります。そのため、労働契約の内容として労使間で合意をし、雇用契約書に記載しなければなりません。
雇用の開始時に、労働条件を明示する義務(労働基準法15条)が会社にあるため、労働条件通知書などを作成して、入社時に示すのが通例です。
就業規則に記載する
労働契約の内容は、雇用契約書に記載するのみならず、就業規則にも書いておくべきです。試用期間のように、対象となる社員全体に適用される制度は、就業規則に定め、全社的に周知するのが便宜です。なお、常時10人を越える社員のいる事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出る義務があります。
就業規則における試用期間の定めについて、次の文例を参考にしてください。
第XX条(試用期間)
1. 新たに入社した社員について、入社日から3か月間を試用期間とする。ただし、社員としての適性を判断するのに不十分であると会社が判断した場合、最長3か月まで延長できる。
2. 試用期間中の社員に、適性がないと会社が判断した場合は、試用期間中もしくは試用期間の終了時に、本採用せずに解雇する。
3. 試用期間は勤続年数に通算する。
複数の雇用形態がある会社では、就業規則の適用対象にも注意が必要です。有期雇用の社員に試用期間を設けようとするなら、契約社員、アルバイト、パートなど、いずれの雇用形態に適用される就業規則にも、上記のように試用期間の定めを置く必要があります。正社員の就業規則だけに記載しても、契約社員に適用されないおそれがあるからです。
契約社員を試用期間で辞めさせるには「やむを得ない事由」が必要
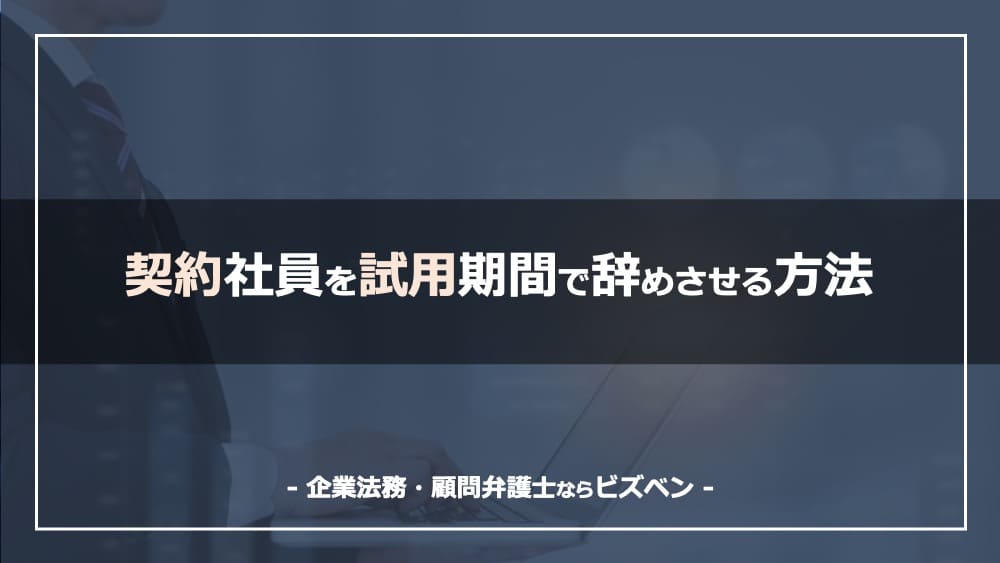
以上の通り、就業規則に定めることで、契約社員でも試用期間を付けることができるとして、それでもなお、試用期間が終了したタイミングで一方的に辞めさせることができるとは限りません。
それは、期間の定めのある雇用契約を解約するには、民法628条において「やむを得ない事由」が必要とされるからです。つまり、会社が、契約社員を期間途中で解雇するには「やむを得ない事由」がなければならないという制約があるのです。
民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法(e-Gov法令検索)
また、労働契約法17条は、民法のルールを更に詳細にし、次のように定めます。
労働契約法17条(契約期間中の解雇等)
1. 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2. 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
労働契約法(e-Gov法令検索)
契約社員は、たとえ試用期間を付けたとしても、その試用期間の満了時はすなわち、まだ有期契約の最中です。したがって、たとえ契約社員に試用期間を設定しても、本採用拒否をするには「やむを得ない事由」が必要です。やむを得ない事由は、解雇に求められる正当な理由よりも、高度な必要性に基づくものでなければなりません。
なお、以上のことを考慮し、試用期間で辞めさせる場合には、試用期間中からできるだけ早めに改善点を伝え、注意指導をしなければなりません。
試用期間ではなく、雇用契約の期間の短縮で対応すべき
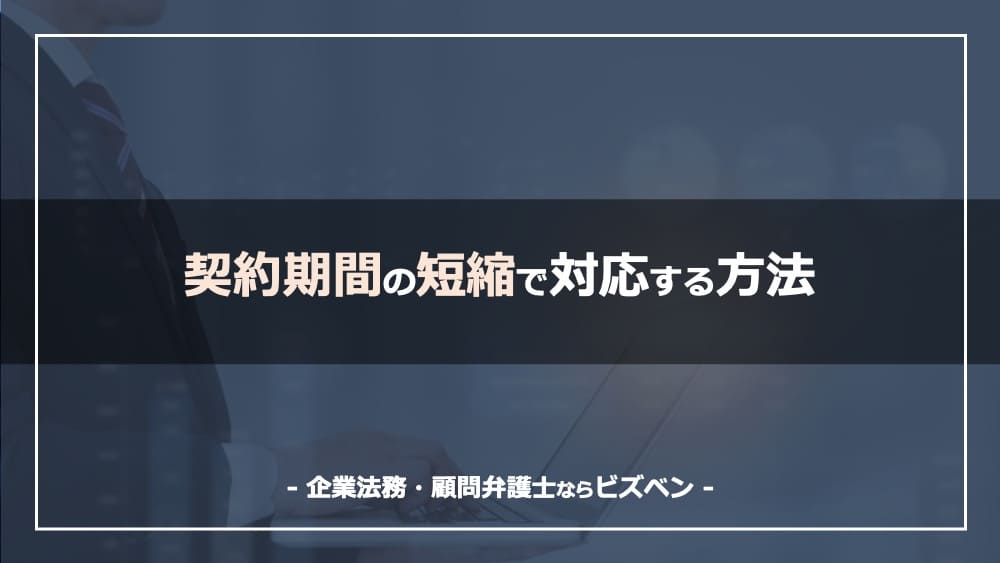
契約社員に試用期間を設定する効果が薄いと理解した上でもなお、「契約社員の能力、適性によって辞めさせたい」というニーズを満たすため、実際の運用をどのようにしたらよいか、解説します。
正社員よりは雇用保障の弱い契約社員といえど、雇い止めの法理によって保護されます。労働者に更新の期待が生まれると、自由に更新拒絶できるわけではありません。そのため企業側にとっては、契約社員の能力、適性を細かく判断していく必要があります。このとき、試用期間を設定して期間を区切るのではなく、そもそも有期雇用契約の期間を短く設定することで同じ効果を生み、目的を達成することができます。
例えば、次のケースを考えてみてください。
【会社の目的】
能力、適性を3ヶ月で判断し、不十分と考える場合には辞めさせたい。
【試用期間で対応する方法】
雇用契約の期間を1年とし、そのうち3ヶ月を試用期間とする。この場合、3ヶ月の終了時に本採用拒否にしようとしても、期間の定めのある雇用を途中で解約することとなり、「やむを得ない事由」がなければ無効となる。
【雇用契約の期間の短縮で対応する方法】
そもそも雇用契約の期間を3ヶ月に短縮する。すると、3ヶ月の期間満了時に、更新するかどうかの判断基準として、能力、適性を評価することができる。
なお、この方法で対応する際にも、不適切なほど短期間の雇用契約を結ぶことは、労働者を不安定な立場に置くため適切ではありません。また、更新の回数が多くなり、期間が長くなるほど、労働者にとって更新の期待につながり、雇い止めの法理によって更新拒絶のハードルは上がりやすくなる点に注意が必要です。
試用期間は「契約社員」として雇用する方法でも、雇い止めは制限される
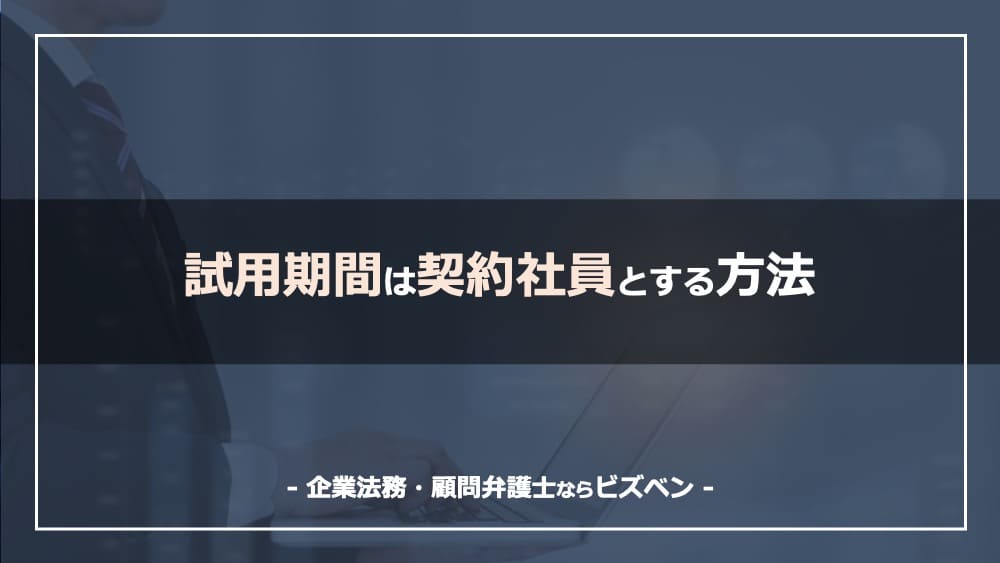
将来は正社員として雇うことを検討していても、その能力や適性に不安があって、まずは契約社員として雇用するケースもあります。つまり、試用期間を、契約社員として雇用する方法です。
この方法では、能力や適性を熟慮できるメリットはもちろん、「正社員として雇いながら試用期間を付する場合」と異なるのは、適切に活用できれば、退職させる際の法的なトラブルを減らせる点にあります。
はじめから正社員として雇うと、たとえ試用期間といえど、本採用されるだろうと強く期待されるおそれがあります。すると、本採用拒否は、期待の裏切りを意味しており、労働者から争われるおそれが高くなります。他方で、試用期間を契約社員として雇っておけば、期間満了で契約終了となるのが原則なので、正社員にしなくても不満は出づらくなります。
ただし、試用期間を契約社員として雇っても、自由に雇い止めできるとは限りません。契約更新について期待があれば、保護される可能性があるからです。
また、裁判例では、試用を目的とした契約社員は、試用期間付きの正社員と同士されると判断したものもあります。裁判所は、契約社員の能力・適格性を判断・評価する目的で期間の定めが設けられた場合、原則として、同期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解すべきと判断しました(神戸弘陵学園事件:最高裁平成2年6月5日判決)。
期間の満了で雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意があるなどの特段の事情がないと、能力、適性がないと判断し、契約社員だからといって辞めさせるのは難しいケースがあります。
また逆に、期間の定めを強調しすぎると、優秀な社員を採用しづらくなってしまいます。
まとめ

今回は、契約社員と試用期間の法律問題について解説しました。
企業側のニーズとして、少しでも人件費を削減し、業績に合わせて雇用を流動化したいことでしょう。この目的は、有期雇用である契約社員を活用すれば、ある程度実現できますが、同時に限界もあります。試しに雇用し、能力、適性を判断し、不要な人員はすぐさま辞めさせるというやり方は、契約社員の雇い止めが制約されるために違法の可能性があります。
契約社員であっても、試用期間を付けることができます。しかし、試用期間はあくまで長期雇用を想定した制度で、契約社員なのにあまりに長すぎる試用期間を設定するのは不適切です。契約社員の管理を徹底したいなら、雇用期間を短めに設定する方法で対応するのがお勧めです。
- 契約社員でも試用期間を付けることができるが、妥当な期間に限らなければならない
- 契約社員に試用期間を付けたとしても、辞めさせるにはやむを得ない事由が必要となる
- 試用期間の間は、契約社員として雇う方法でも、結局のところ雇い止めは制限される
\お気軽に問い合わせください/


