事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物所有を目的として、期間を定めて土地を借りる権利です。借地権の設定は、事業に要する不動産を保有していない企業にとって欠かせない契約。なかでも、事業用定期借地権は、ビジネスの場面での貸主と借主の利益調整として機能する、とても重要な契約となります。
事業用定期借地権は、期間満了によって当然終了する一方で、貸主から中途解約できないのが原則です。そのため、継続的な土地活用が保証され、安定した収益を確保できます。
しかし、事業用定期借地権の設定の際、契約書のチェックは入念にすべきです。ビジネス目的の借地権は、不利な内容の契約だったり、不測の事態が起こったりすると、会社の損失となるからです。事業用定期借地権の設定には、公正証書が必要であるなど、厳密な手続きがあります。期間が限られることで、更新するか争いになったり、建物買取請求権がなかったりなど、貸主とのトラブルも起こりがちです。
今回は、事業用定期借地権の設定契約の流れと、公正証書、契約書の注意点を、企業法務に強い弁護士が解説します。
事業用定期借地権とは
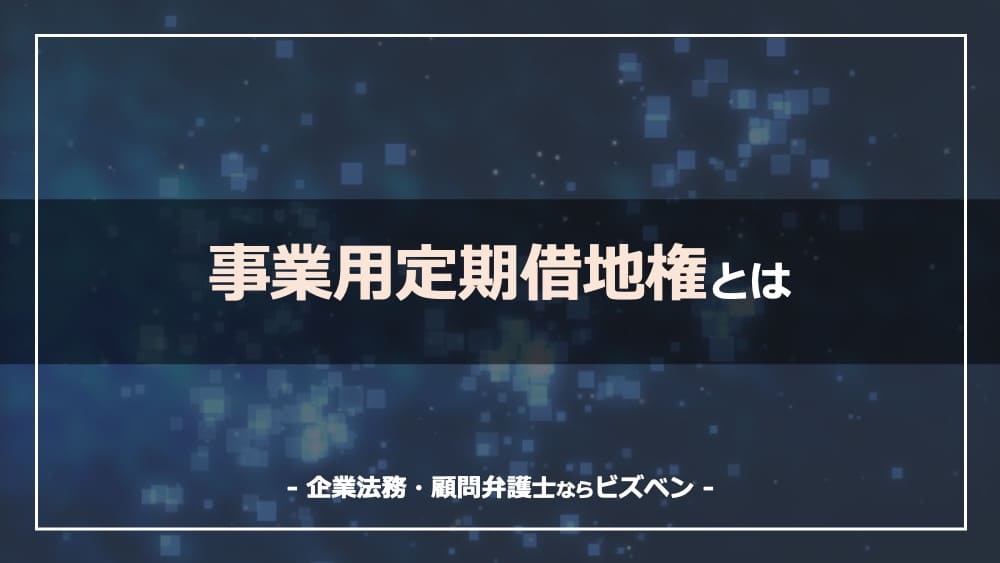
事業用定期借地権とは、定期借地権のうち、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものです。
事業用定期借地権の期間は、従来は、契約期間を10年以上20年以下とされていましたが、借地借家法の改正で、2008年1月1日移行は、10年以上50年未満とされています。
定期借地権は、通常とは異なり、期間の定めを重視した借地権。借地権は、借主の弱い立場を保護するため、借地借家法により、解約、更新拒絶には正当な事由を要するものとされ、信頼関係の破壊が著しい場合でなければ借主を追い出せません。これに対し、定期借地権なら正当な事由がなくとも期間満了によって当然に終了します。その一方、貸主側からも、期間途中の解約を許さないのが原則とされ、期間中は借主の保護が図られます。
借地借家法の定める定期借地権は、次の3種類です。
- 一般定期借地権
(借地借家法22条)
契約の存続期間を50年以上とする借地権。契約の不更新、建物買取請求権の不行使を特約することができる。特約を定める場合には、公正証書による契約を要する。 - 事業用定期借地権
(借地借家法23条)
土地の利用目的が、事業用建物の所有に限定される借地権。契約の存続期間は10年以上30年未満か、30年以上50年未満の2通り。10年以上30年未満の契約なら、契約の更新、建物再築による存続期間の延長、建物買取請求権がない(30年以上50年未満の契約でも、特約で同様の定めが可能)。公正証書による契約を要する。 - 建物譲渡特約付借地権
(借地借家法24条)
契約の存続期間を30年以上とし、30年以上経過した段階で、借地上の建物を借地権設定者に売り渡すことを合意する契約。建物の譲渡後によって借地権は消滅するが、その後も借地人が建物を使用し続けるときは、建物については期間の定めのない賃貸借契約が成立したとみなされる。
事業用定期借地権の特徴
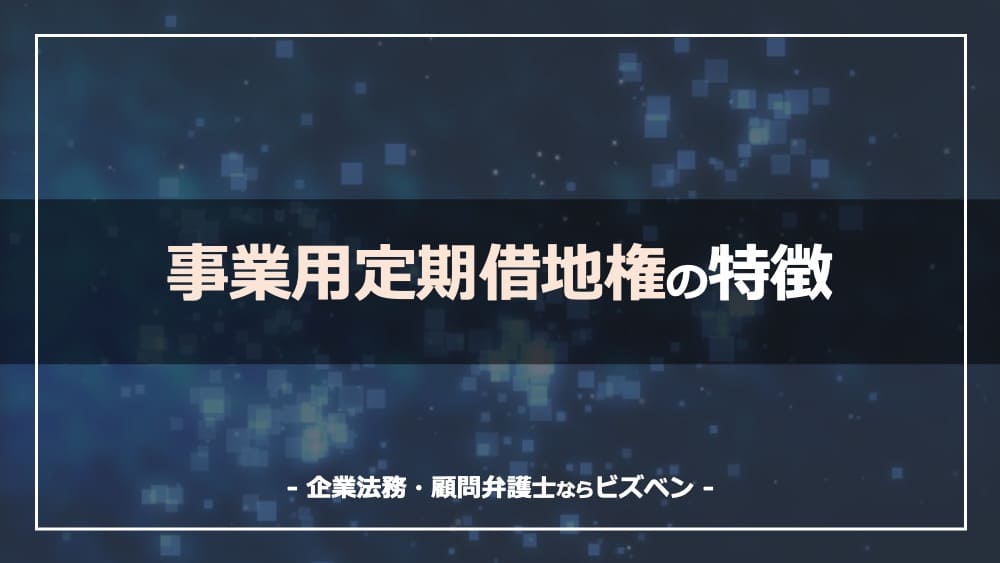
事業用定期借地権を活用するには、どのような特徴があるかを知る必要があります。
それぞれの特徴は、貸主、借主のいずれにとっても一長一短あるため、自社のビジネスの目的に、事業用定期借地権が適切かどうか、よく検討しなければなりません。
事業用の目的に限定される
事業用定期借地権は、その目的が、事業用の建物所有に限定されます。つまり、借りた土地の上に建物を建てて、その建物をビジネスのために利用する場合に限られ、その建物が居住用の場合は、事業用定期借地権は設定できません。
たとえ収益を目的としていても、アパートやマンションの建築は不可となります。社員寮とする場合や、店舗兼住宅、SOHOといった目的で使用することもできません。
事業用定期借地権の期間は「10年以上30年未満」「30年以上50年未満」の2通り
事業用定期借地権の存続期間は、従来は、契約期間を10年以上20年以下とされていましたが、借地借家法の改正で、2008年1月1日移行は、10年以上50年未満とされています。
そのうち、「10年以上30年未満」と、「30年以上50年未満」とでは、次章の通り、特約に関する定めが異なります。なので、事業用定期借地権は2パターンに区分されていると考えてよいでしょう。2つの区分を柔軟に選択できるようになり、事業用定期借地権を利用した土地活用は、今後増加すると予想されます。
契約の更新、建物再築による存続期間の延長、建物買取請求権がない
事業用定期借地権は、その期間を重視した借地権で、期間満了によって終了するのが原則です。そのため次の通り、法律上の定め、もしくは特約によって、契約更新及び建物買取請求権について、通常の借地権とは異なる扱いとなります。
- 10年以上30年未満の契約とした場合
契約の更新はなく、建物再築による存続期間の延長もない。また、契約期間の満了時に、建物買取請求権も発生しない点も、通常の借地権とは異なる特徴。 - 30年以上50年未満の契約とした場合
上記のルールは当然には適用されないが、特約で同様に定めることができる。
公正証書による設定契約が必要
事業用定期借地権の設定契約は、公正証書で行う必要があります。公証役場で、公証人の認証を受けなければなりません。口頭の約束では設定できないのは当然、通常の借地権や、他の契約のように、契約書を作成、締結しても、それだけでは、事業用定期借地権は設定できません。
公正証書がないと、事業用定期借地権は成立しないものの、普通借地権の設定と扱われる可能性があります。
すると、契約期間が終了した後も、正当な事由のない限り、借地借家法に基づいて更新され、賃貸人にとって不測の損害となってしまいます。期間満了で返還されると思っていた土地が、永久に戻ってこない危険があります。
事業用定期借地権のメリット・デメリット

事業用定期借地権には、賃貸人、賃借人のいずれにとっても、メリット、デメリットがあります。
賃貸人のメリット
賃貸人にとって、通常の借地権よりも賃借人の保護の薄い点が最大のメリットです。これにより、契約期間が満了すれば土地の返還を受けられ、10年〜50年の中期的なスパンで、計画的に土地を活用できます。建物買取請求権がなく、賃貸借の終了時は、更地にして返還される点も、事業用定期借地権のメリットです。
一方で、事業用定期借地権だと、期間途中に解約される可能性がないことから、賃借人も一定の投下資本を回収すべくビジネスを行います。賃貸人にとっても地代収入が定期的に続くメリットがあり、立ち退きのトラブルや、テナントの中途退去のリスクを回避できます。
賃貸人のデメリット
賃貸人にとっての事業用定期借地権のデメリットは、契約期間の途中で解約ができないことです。
したがって、事業用定期借地権の設定契約では、期間の定めに特に注意を要します。定めた期間の途中で、その土地を自社で利用したいと気が変わっても、解約して賃借人を立ち退かせることはできません。また、期間中は保護されるために賃借人は撤退しづらく、万が一賃借人が倒産すると、土地上の建物を壊し、明け渡させるために、法的な手続きを要します。
賃借人のメリット
賃借人にとっては、通常の借地権よりも保護が薄い反面、賃貸人にとって気軽に貸しやすくなり、好立地の土地を、低コストで利用することができる点が、事業用定期借地権のメリットとして挙げられます。
期間についても、10年以上30年未満、30年以上50年未満の2パターンから、事業の目的に沿った最適なプランを選択することができ、30年以上50年未満を選択する場合には、賃貸人と交渉することで、建物買取請求権を確保することも可能です。
賃借人のデメリット
賃借人にとっての事業用定期借地権のデメリットは、通常の借地権よりも保護が薄い点です。
更新ができず、契約終了時には更地で返さなければならない点は、賃借人にとって大きな負担となります。事業計画をよく練らなければ、投下資本を回収する前に立ち退かざるを得なくなります。
事業用定期借地権の設定契約の流れ

事業用定期借地権を正しく活用するには、設定契約の流れを知る必要があります。
まず、公正証書の元となる当事者の合意をする必要があります。
賃貸人、賃借人の間で、諸条件を話し合い、合意に至った内容を合意書、覚書といった書面にしておくのがお勧めです。公正証書が完成しなければ事業用定期借地権は成立しないものの、それまでの間に態度を変えられてしまわないよう、合意ができた時点で書面化し、証拠に残しておきましょう。
事業用定期借地権の設定には、公正証書を要します。公正証書は、公証役場において公証人の認証を受けて作成する書面。公正証書の作成には、まず当事者間で合意した内容を書面にし、公証人のチェックを受ける必要があります。
最後に、事業用定期借地権の設定登記をします。
事業用定期借地権は、登記をすることで第三者に対抗できます。例えば、貸主が借主に無断で底地を譲渡したケース、借主が貸主に無断で建物を譲渡したケースなどで、登記による対抗力が争点となります。
事業用定期借地権の契約書(公正証書)のひな形
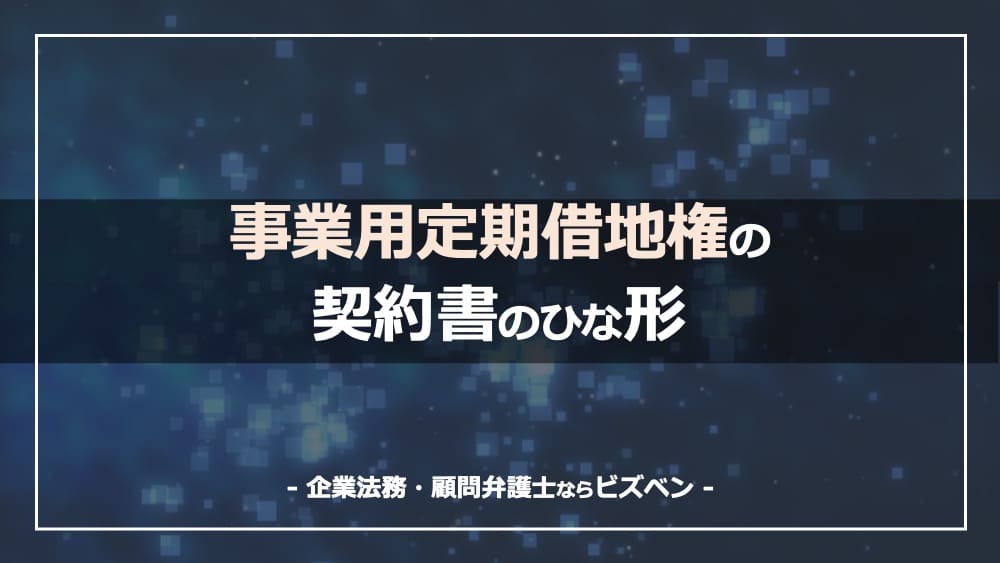
次に、事業用定期借地権の契約書(公正証書)のひな形を紹介します。事業用定期借地権設定契約書は、「設定合意書」「覚書」といった様々な名称で呼ばれることがあります。
いずれにせよ、公正証書を作成することが事業用定期借地権を設定する条件となので、その元となる書面による契約書の作成は必須となります。
事業用定期借地権設定契約書
賃貸人XXXX(以下「甲」という。)及び賃借人YYYY(以下「乙」という。)は、甲所有の別紙目録記載の土地(以下「本件土地」という。)について、事業用定期借地契約(以下、「本借地契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
1. 本契約は、○○○事業(以下「本事業」という。)の実施のため、別紙1に示す建物群(以下「本件建物」という。)を乙が建設して所有することを目的として本件土地に借地借家法(以下「法」という。)23条1項に定める事業用定期借地(以下「本件借地権」という。)を設定することを目的とする。
2. 本件借地権は、法9条及び16条の規定に関わらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長はなく、また、乙は、法13条の規定による建物の買い取りを甲に請求することはできない。
3. 本件借地権には、法3条から8条まで、13条及び18条並びに民法619条の規定の適用はないものとする。
第2条(用途)
1. 乙は、本件土地を本事業の用に供する本件建物の敷地として、また、その余の部分をその建物に付随する業務上必要な付属施設の設置用地として使用するものとし、他の用途に使用しない。
2. 乙は、本件建物、付属施設を居住の用に供してはならず、本件土地上に居住のように供する建物を建築してはならない。
3. 乙は、事前に甲の書面による承諾がない限り、本件建物の増改築、本件土地上の付属施設の建設、増改築を行ってはならない。
第3条(賃貸借期間)
1. 本件土地の賃貸借期間は、2022年11月1日から2062年10月31日までとする。
2. 前項の賃貸借期間には、本件建物の建築に要する期間及び解体・撤去等の原状回復に要する期間を含むものとする。
第4条(賃料)
1. 本件土地の賃料は、月額XX万円とし、乙は甲に対して、毎月25日限り、その翌月分を甲が指定する下記銀行口座に振り込む方法によって支払う。振込手数料は乙の負担とする。
2. 前項の規定に関わらず、賃料が、本件土地に対する租税その他の公租公課の増減、近隣の土地価格の変動その他の経済事情の変動、または近隣類似の土地の賃料に比較して不相当となったときは、甲又は乙は、相手方に対して、将来に向かって賃料の増減を請求することができる。
第5条(権利金)
1. 乙は、本契約締結日に、甲に対して、本件借地権設定の権利金として金XXX万円を前条1項の方法により支払う。
2. 前項の権利金は、理由の如何に関わらず返還しない。
第6条(保証金)
1. 乙は、本借地契約に関して生ずる乙の債務の担保として、本契約締結日に、甲に対して保証金として金XXX万円を預託する。保証金には利息を付さない。
2. 甲は、本借地契約が終了し、乙から本件土地の引渡を受けたときは、引渡の日から2か月以内に前項の保証金から延滞金等の乙の甲に対する債務を控除した残額を返還する。
3. 乙は、保証金返還請求権をもって甲に対する賃料その他の債務と相殺することはできない。
4. 甲は、乙が、賃料、損害賠償その他の本借地契約に基づく甲に対する金銭債務の支払を遅滞したときは、甲は書面による催告のうえ、第1項の保証金の全部又は一部をその弁済に充当することができる。
5. 前項の場合、乙は、充当の通知受領後1か月以内に、第1項の金額に満つるまで保証金を預託しなければならない。
6. 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、または、担保に供してはならない。
第7条(借地権の譲渡・転貸の禁止)
乙は、第三者に借地権を譲渡し、または、本件土地を転貸することはできない。
第8条(契約の解除)
(略……詳しくは「契約期間の定めと中途解約条項」参照)
第9条(契約不適合)
乙は、本借地契約の締結後、本件土地について数量の不足その他の契約不適合があることが判明したとしても、第4条の賃料、第5条の権利金及び第6条の保証金の減額、損害賠償の請求、本借地契約の全部又は一部の解除その他の一切の請求をすることはできない。
第10条(免責)
地盤沈下、震災、風水害、その他甲の責めに帰すことができない自由により乙が被った損害については、甲は一切の責任を負わない。
第11条(費用負担)
1. 甲は、本件土地に対する公租公課を負担する。
2. 乙は、本件建物に対する公租公課及び本件建物の維持管理費その他の一切の費用を負担する。
第12条(土地の譲渡)
甲が本件土地を第三者に譲渡した場合は、本件土地の譲受人に対して、本契約の権利義務の一切を承継させる。
第13条(建物等の撤去及び土地明渡し)
1. 乙は、賃貸借契約期間の満了、もしくは、解除、解約により本契約が終了した場合は、終了日までに本件土地を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
2. 乙が、終了日までに本件土地の明渡しをしないときは、乙は、甲に対して、本契約終了の日の翌日から明渡しに至るまで、本契約終了時の賃料の2倍相当額を遅延損害金として支払う。
3. 乙が、本件土地上の建物等の収去義務を怠ったときは、甲は前項に定める遅延損害金のほかに、建物収去工事費の相当額を請求することができる。
第14条(事業用定期借地権の設定)
1. 甲は、乙が本件土地に対し、賃貸借期間中、事業用定期借地権の設定登記をなすことを承諾し、登記手続に協力する。
2. 本契約が終了したときは、乙は速やかに設定した事業用定期借地権の抹消登記手続を行う。
3. 前2項の登記手続費用は、乙の負担とする。
第15条(公正証書作成)
1. 甲及び乙は、本借地契約を内容とする公正証書の作成を公証人に委嘱する。
2. 乙は、前記公正証書に本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨認諾する文言を付することを約した。
3. 前2項の公正証書の作成に要する費用は、乙の負担とする。
第16条(解釈)
本借地契約に定めのない事項及び各条項に疑義が生じたときは、甲乙協議して定める。
第17条(管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約に関する訴訟については、本件土地の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意した。
事業用定期借地権の契約書(公正証書)の注意点

事業用定期借地権の設定は、借主側にとっては事業の成功のために必須であり重要なのは当然。また、貸主側にとっても、低リスクでの土地活用を実現するのに大切なことに変わりはありません。
そのため、事業用定期借地権の契約書(公正証書)は、自社に不利な条項がないかよく検討しなければなりません。最後に、事業用定期借地権を定める契約書の注意点について解説します。
目的条項を定める
事業用定期借地権の契約書には、その設定目的が「事業」にあると明記する必要があります。例えば「事業の用に供する建物の所有を目的とする」などといった文言を入れることが考えられます。
用途を定めると、用途に違反した場合には解約されるおそれがあります。たとえ事業用定期借地権といえど、賃借人の債務不履行、義務違反を理由とする場合には、中途で解約することができるので、注意を要します。
契約期間と特約について適切に定める
前章の通り、事業用定期借地権は、存続期間を10年以上30年未満とするか、30年以上50年未満とするかによって特約の扱いが異なります。前者の場合には、法律によって当然に、更新、建物再築による存続期間の延長、建物買取請求権がなくなりますが、後者の場合には特約によって選択できるため、特約を付すかどうか、当事者の話し合いに委ねられます。
このように扱いが異なる点も踏まえて、適切な契約期間を定める必要があります。また、特約の有無について、賃貸人と賃借人とで利害が反することがあるため、自社にとって不利にならないよう粘り強く交渉しなければなりません。
強制執行認諾文言を入れる
賃貸人側にとっては、公正証書に、強制執行認諾文言を盛り込むことが大切です。
公正証書のメリットの1つとして、裁判による判決を得なくても強制執行が可能となる点が挙げられます。しかし、このメリットを享受するには、公正証書に、強制執行を認諾するという記載をしておく必要があります。
この定めがあれば、賃借人による賃料未払いがあったとき、裁判することなく賃借人の財産を差し押さえることができます(事業用定期借地権ならば、土地上に建設した建物が、真っ先に差し押さえ対象の財産として挙げられます)。
強制執行による債権回収の解説についても参考にしてください。

まとめ

今回は、事業用定期借地権について解説しました。設定契約の流れをよく理解し、公正証書、契約書について注意深くリーガルチェックするようにしてください。
借地権は、事業を遂行する場の確保であり、特に店舗ビジネスにとっては欠かせません。想定していた通りの権利が得られていないと、事業が立ち行かなくなる危険もあります。事業用定期借地権を設定し、厳格な手続きで進めるべきケースには、相応のリスクも内在しているため、弁護士の専門的なサポートが有益です。


