契約書に記載する内容によっては、契約期間を定めておいた方が良いケースがあります。契約は、権利を得たり、義務を負ったりするものであり、無期限だとすれば過大な義務を負いかねないからです。
契約期間を定めるとして、どのような期間とするか、迷うことがあります。契約書を作成するときにも、始期と終期、更新条項の有無、中途解約条項の有無など、契約期間に関する多くのポイントに配慮せねばなりません。一方で、契約の内容・性質によっては、契約期間を定める必要のない契約書もあります。
「一般的な契約期間」「契約期間の相場」を知りたいという質問もありますが、そのビジネスの内容に応じ、個別に検討しなければなりません。契約期間と、途中で解約できるかどうかを定めておかないとトラブルのもとです。紛争を回避するためにも、契約書を結ぶ段階から、中途解約を想定して条項を記載すべきです。
今回は、契約期間と、中途解約条項の定め方を、具体的な例文をもとに、企業法務に強い弁護士が解説します。
契約期間を定める理由
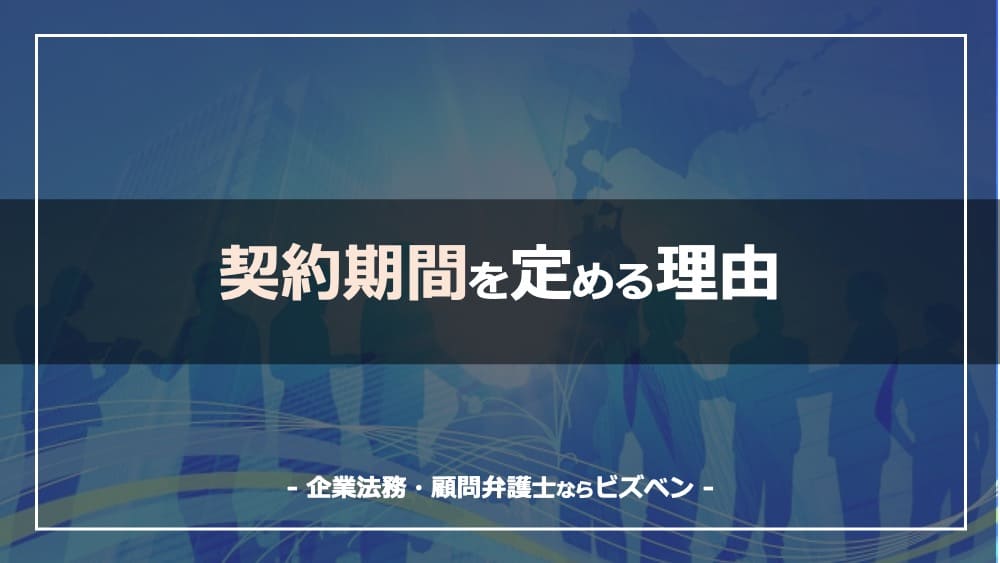
大前提として、そもそも、なぜ契約期間を定める必要があるのか、理解せねばなりません。つまり、契約期間を定める理由があるかという点です。
契約期間の必要性は、その契約の種類、内容、性質によって異なりますが、結論として、ビジネスの取引について定める契約では、契約期間を定める必要のある場合がほとんどです。ビジネスでは、全く無関係の第三者が、互いに信頼関係を構築し、取引します。その信頼は、利益のある限りにおいてしか続かない限定的なもので、永続はしません。
例えば、次のビジネス上の契約は、契約期間を定めるのが通例です。
- 従業員などを使用する際の契約
(労働契約、派遣契約、個人事業主との業務委託契約など) - 継続的な仕入れ契約
- ビジネス取引を委託する契約
(代理店契約、販売店契約、フランチャイズ契約など) - 知的財産に関するライセンス契約
- M&Aを検討する際の秘密保持契約書
- 協業するための契約
(合弁契約など)
契約は、権利を得られるメリットがある一方、義務を負うデメリットがあります。契約期間の定めがなく、義務が長期にわたって続くとすれば、会社の負担が過大になるおそれがあります。
したがって、継続的な取引関係を結ぶ場合には、必ず契約書に、契約期間を定めてください。
なお、1回きりの契約であれば契約期間を定める必要はありませんが、その取引が重要ならば、秘密保持契約書や基本合意書などの契約を交わす例も多く、それらから生じる義務を限定するにも、契約期間が必要です。
1回きりで終了する売買契約などの例では、契約期間でなく、履行期限を定めておくべきです。この場合、その1回の取引が終了すれば、契約書は役目を終えます。
契約期間の定め方
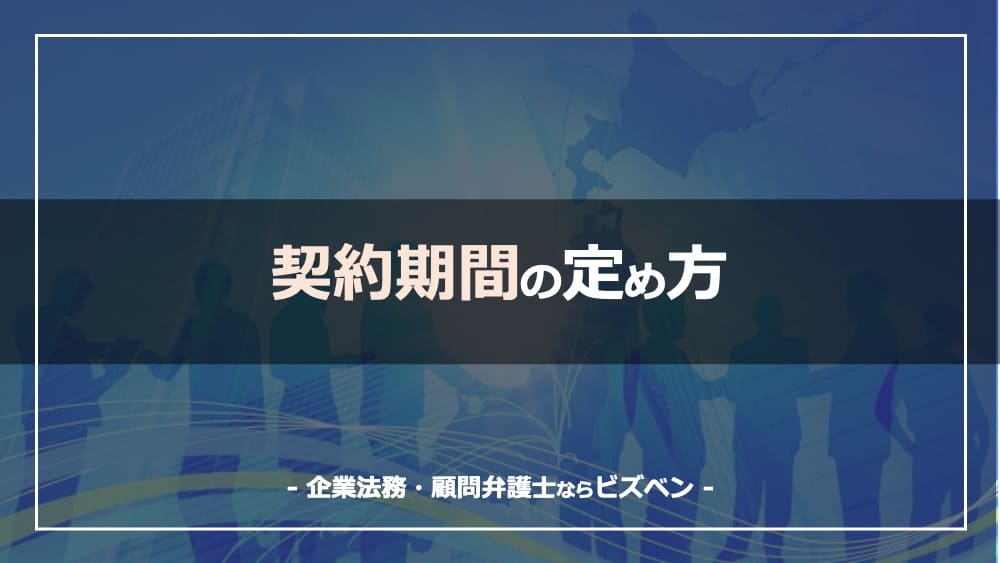
契約期間を定める必要があるとして、次に、具体的な例文を紹介しながら、契約期間の定め方を解説します。
契約書の定め方のポイントとして、一義的に、かつ、明確に規定することが大切です。つまり、契約書を読めば「誰の目から見ても争いがない」という記載内容とすべきです。逆に、抽象的であったり曖昧だったりして、読み方が複数あるような定め方だと、かえって争いのもとです。
契約書は、紛争に備えて作成するので、争いを抑えてくれなければ事前に作成する意味がありません。
始期と終期を定める方法
契約書において契約期間を定める場合に、始期と終期を定めることで、契約期間を特定する方法がよく用いられます。始期と終期をそれぞれ、具体的な日時で指定すれば、契約期間の定めは一時的に明らかだといえます。次の契約書の例文を参考にしてください。
第XX条(契約期間)
本契約の期間は、20XX年XX月XX日から20YY年YY月YY月日までとする。
始期、終期は、具体的な年月日が分かれば、どのような特定の仕方でも構いません(西暦でも和暦でも変わりませんし、「第1土曜日」といった定め方でも特定可能です)。ただ「吉日」などといった記載は、具体的にいつを指すか不明確なため、不適切な定め方と言わざるを得ません。
期間によって定める方法
契約書で、始期と、契約期間の2つを定め、契約期間を特定する方法もあります。次の契約書の文例を参考にしてください。
第XX条(契約期間)
本契約の期間は、20XX年XX月XX日からYY年間とする。
終期を記載しなくても、始期からの期間が明らかになっていれば、契約期間を一義的に定めることができます(なお、この場合には、次章の通り、契約期間の数え方に注意しなければなりません)。
この定め方では、始期を「本契約書の締結日」とする例があります。
しかしこの場合、契約書に実際に署名した日と、契約書に印字された日が違う場合に、どちらの日を始期とするか、争いが生じるリスクを回避できません(契約書をバックデイトした場合など)。
契約期間の数え方
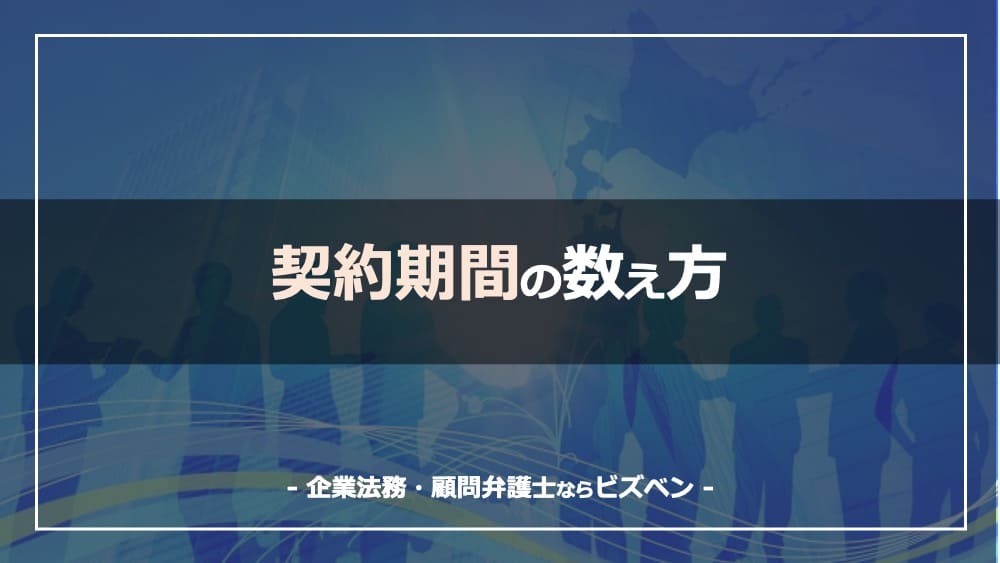
前章の通り、契約書上で始期、終期が明らかならよいですが、始期と契約期間しか記載しない場合は、その期間の数え方が問題となります。
法律上の期間の計算方法には、初日不算入の原則を始めとした特殊なルールがあります。よく注意しないと、気付いたら期限を過ぎていたというケースもあります。一般的な数え方とは異なることもあるため、法律上のルールをを理解しないと、契約期間を正確に算定できません。
初日不算入の原則
民法のルールで、期間の計算方法のうち、最重要なのが「初日不算入の原則」。つまり、日、週、月、年によって期間を定めた場合、初日は算入しないこととする決まりです(ただし、初日が丸一日算入できる場合には初日も計算することとなっています)。初日不算入の原則を定める民法の規定は次の通りです。
民法140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。
民法(e-Gov法令検索)
わかりやすく言えば「24時間未満の期間は、算入しないルール」ということ。初日不算入の原則によって、契約期間の始期が正確に特定されます。
日単位で定めた契約期間の計算
初日不算入の原則で契約期間の始期が特定されたら、次に、その期間を「日単位」で定めた場合、末日の終了によよって期間が満了することと定められています。「日単位」で定めるケースとは、契約書の条文において終期が「20YY年YY月YY日まで」のように具体的な日で特定されている場合です。
ただし、末日が日曜・祝日で、その日に取引をしない慣習がある場合は、契約期間の末日の翌日に、期間が満了することとなっています。ビジネス上の契約であれば、土日休みの会社が多い業界なら、期間の末日が日曜なら、月曜に終期が来ることになります。
この点を定めた民法の条文は、次の通りです。
民法141条
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
民法142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
民法(e-Gov法令検索)
週・月・年単位で定めた契約期間の計算
契約期間を、週、月または年単位で定めた場合には、暦に従って計算します。そして、終期は、最後の週、月、年における「起算日に応当する日の前日」に終了します。なお、日による期間と同じく、末日が休日ならその翌日に満了となります。
月の総日数は、各月ごとに異なるため、応当日のないときはその月の末日が契約期間の満了日となります。そのため、月の日数が30日か、31日か、閏年かどうか、といった事情によっても契約期間は一義的に決まるルールとなっています。
この点を定めた民法の条文は、次の通りです。
民法143条
1. 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2. 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
民法(e-Gov法令検索)
自動更新条項のポイント

次に、契約期間と関連して、自動更新条項について、その例文とポイントを解説します。
契約期間を定めた契約では、期間が満了すれば取引関係は終了するのが原則。しかし、継続的な取引関係は信頼によって成り立っており、信頼が崩れないなら、できる限り長期に継続したほうがメリットのあるケースもあるでしょう。企業間の継続的な取引を続けるメリットは、次の点です。
- 新たな取引相手を探す必要がない
- これまでに蓄積した取引マナーを継続できる
- 現場の心理的なストレスを軽減できる
一方で、当事者のいずれかの業績が大きく変化した場合などには、契約を解約したり、損害賠償請求したりといった責任追及をできるよう、中途解約条項とはセットで定めるべきです。
継続的な取引関係を長期に渡って続けるとき、契約期間が満了するごとに新しい契約書を締結したり、契約条件の交渉をし直したりするのは手間であり、予想外のトラブルを起こすきっかけにもなりかねません。そこで、再契約の際の手間とコストを減らし、これまで続いた信頼を崩さないために、自動更新条項を追加するケースが多くあります。
自動更新条項の例文
自動更新条項の具体例は、次の例文を参考にしてください。自動更新の理由となる信頼関係の強さ、将来どれほどの期間だけ契約を継続する予定か、といった事情により、自動更新条項の例文には様々なパターンがあります。
【双方に異議がなければ自動更新される場合】
本契約の期間は、20XX年XX月XX日から20YY年YY月YY日とする。
ただし、期間満了日の1ヶ月前までに、いずれの当事者からも異議のない場合は、本契約と同一の条件でさらにX年更新されるものとし、その後も同様とする。
【片方に異議がない限り自動更新される場合】
ただし、期間満了日の1ヶ月前までに、甲が乙に対して書面で異議を述べない限り、本契約と同一の条件でさらにX年更新されるものとし、その後も同様とする。
【合意があれば自動更新する場合】
ただし、期間満了日までに甲乙が更新することに合意した場合、本契約と同一の条件でさらにX年更新されるものとし、その後も同様とする。
【更新を1回に限る場合】
ただし、……(略)……。更新の回数は1回限りとする。
以下では、自動更新条項を定める際の注意点を解説します。
自社側で契約書を作成する場合は当然、相手方から、自動更新条項のついた契約書の提案を受けたときには、自社にとって不利な内容がないかどうか、契約書のリーガルチェックは欠かせません。
自動更新される条件を明確に定める
自動更新条項の注意点の1つ目は、自動更新される条件を、明確に契約書に定めること、つまり「どのような場合に自動更新の効果が生じるか」という点を明らかにすることです。
例えば、上記1つ目の例文だと、「期間満了の1ヶ月前までに、当事者いずれからも異議がない」ということが、自動更新の効果が生じる条件として定められています。重要なポイントは、「更新するかどうかを決定できるのが、いずれの当事者か」という点。契約における力関係の差から、いずれか一方にしか更新を決める権利がない定め方も可能です。
このことは、「更新について放置したまま、契約期間が満了した」という場面で違いが出ます。
「何もしないと契約が自動的に更新される」という定め方か、それとも「何もしないと契約が終了する」という定め方かに注意してチェックしましょう。
更新拒絶できる条件を明確に定める
自動更新条項の注意点の2つ目は、更新拒絶できる条件を明確に定めること、つまり「どのような場合に、いずれの当事者が更新をストップすることができるか」を明らかにすることです。
更新拒絶できる期間の長さによっては、不当に一方当事者の権利を侵害したり、長すぎる期間の拘束を受けてしまったりすることにもなりかねません。期間満了よりもかなり前に「更新するかどうか」を判断しなければならないとすれば、信頼関係がまだ築けていない段階で、継続契約の有無について判断を迫るという不適切な状況にもなりかねません。契約期間はもちろんのこと、更新拒絶できる期間もまた、適正な期間を定めるべきです。
更新後の契約条件を定める
更新を前提とする契約では、更新後の契約条件についても定めておかなければなりません。
「更新前と同条件で更新する」と定める例が多いです。自動更新条項の趣旨が、期間満了ごとの交渉の手間を減らす点にあり、条件変更をなくす方がメリットが大きいからです。ただし、契約更新は、条件変更の良い機会でもあるので、一定の場合には、「更新の際に当事者の協議を要する」と定めることもできます。
複数回の自動更新が可能か定める
最後に、自動更新を複数回予定しているかどうかも、検討してください。複数回更新される方が良いと考えるなら「再契約後の契約も、自動更新できる」旨の条項を定めておきます。
実際の契約書では、簡易的に「その後も同様とする」と定める例が多いですが、これも同じ意味で、更新後の再契約が満了した後も、自動更新条項の適用があることを示す条項です。この記載が抜けていると、再契約の期間が満了したときに、それで終了となるのか、それとも更に自動更新されるのかが不明確になってしまいます。
中途解約条項のポイント

次に、契約期間と関連して、中途解約条項について、その例文と注意点を解説します。
企業間の取引は、継続的な関係となります。前章の自動更新条項を設ける例は多いものの、あくまで信頼関係が継続している範囲内でのこと。信頼関係は、将来崩れてしまう可能性もあり、あまりに長期に、契約期間の拘束を受けることは、むしろリスクもあります。もっと良い取引相手が出現することもあるでしょう。将来事情が変わったときは、契約期間の途中でも取引を終了する必要があり、中途解約条項をあわせて定めるべきです。
中途解約の条項がなくても、まったく中途解約できない契約書というわけではありません。
条項がなくても、債務不履行があれば契約を解除できますが、その場合、民法のルールに従う必要があります。すると、相手に責任のない限りは、契約に拘束されることとなり、ビジネス上の大きなリスクとなります。
中途解約条項の例文
中途解約条項の具体例は、次の例文を参考にしてください。中途解約をする必要のある場面を事前に想定し、列挙する必要があります。
第X条(中途解約)
- 甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、または違反するおそれがあると認めたときに、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の違反または違反するおそれが是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
- 甲及び乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、通知なくして本契約を直ちに解除することができる。
一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき
二 会社更正手続または民事再生手続の開始、破産の申立をなしたとき、または、第三者からこれらの申立がなされたとき
三 資本減少、営業の廃止もしくは重要な部分の変更、譲渡または解散の決議をしたとき
四 本契約遂行に必要な許認可を取得できず、またはその失効・停止処分をうけたとき
五 相手方またはその関係者を誹謗中傷し、またはその名誉・信用を棄損したとき
六 その他前各号に準ずる信用の悪化、信頼関係の悪化と認められる事実が発生したとき - 前2項により解除した当事者は、相手方に対して、解除により生じた損害の賠償を求めることができる。
以下では、中途解約条項を定める際の注意点を解説します。
中途解約できる条件を明確に定める
中途解約条項において、どのようなとき中途解約できると定めるかが最重要です。
中途解約できる場面が限定的だと、契約の拘束力が強すぎます。しかし、中途解約があまりに容易だと、契約上の地位が極めて不安定になり、信頼して長期の契約関係を結んだ意味が薄れてしまいます。
どのような会社やビジネスでも中途解約を希望するであろう、相手の契約違反や業績不振、倒産などといった事情を列挙して定めるのが通例です。
双方向的に同じ条件とする場合もありますが、そうでなく、一方からの中途解約のみ容易にできるように定めることも可能。したがって、契約当事者の力関係次第では、自社のみ中途解約を容易にする規定もあります。
中途解約の方法を定める
中途解約できる条件を満たすときに、どのような方法で中途解約するかについても具体的に定めます。特に次の点に配慮するようにしてください。
- 事前通知を要するか、即時に解約できるか
中途解約の条件ごとに、その責任の度合いに応じて事前通知の有無を定めることができます。 - 事前通知を要する場合、通知期間の長さ
事前通知の期間があまりに長すぎると、ビジネス上の不都合があったとき速やかに解約する支障となります。一方で、事前通知の期間が短すぎると、修正できたはずの契約違反などで、信頼関係を回復するチャンスがなくなってしまいます。 - 中途解約するのに書面を要するか、口頭でも可能か
中途解約は非常に重大で、トラブルの起きやすい場面。書面による通知を要すると定めるのが良いでしょう。
どの程度の丁寧な手続きを要するかは、契約の種類、契約期間の長さ、契約当事者の信頼関係の濃さなどによっても異なるため、様々な事情を総合的に考慮して決定します。
中途解約時の損害賠償について定める
最後に、中途解約した際の損害賠償についても定めます。中途解約を検討する場面では、解約される側に責任があると考えられるケースもあります。このとき、債務不履行があれば民法のルールに従って損害賠償請求できますが、そのことを確認的に定めておく例が多いです。
例えば「中途解約をした場合、損害賠償請求をすることは妨げられない」といった例文です。解約によって自社側に損害が生じることが予想されるケースや、その損害を証明するのが困難だと考えられる場合には、違約金の定めを置く例もあります。
契約書の損害賠償条項のポイントは、次に詳しく解説します。

まとめ

今回は、契約書における契約期間と、中置解約条項の定め方について解説しました。契約書を作成するときは当然、提案された契約書をチェックするときにもよく理解すべきです。
継続的な取引関係ほど、信頼関係をベースにしており、いざトラブルとなったときその被害は拡大しがちです。リスクを負わないためには、契約期間と更新、中途解約条項の定め方が非常に重要です。特に、企業間で、ビジネスにおいて取り交わされる契約書は、継続的な関係となるのが通例で、よく注意しなければなりません。
契約期間が、ビジネスモデルに最適の期間とされていないと、かえって不利益を被ります。まして、企業間の取引で、無期限とすべきケースは稀でしょう。中途解約についても、一方的に不利な内容となっているなら、法的な観点から慎重な修正を要します。解約時の責任追及こそ、大きな紛争に発展することが多いからです。


