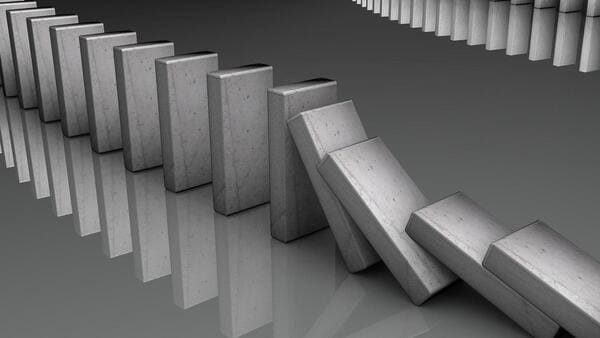借金の返済が苦しくなってきた方が、検討すべき選択肢の一つが「個人再生」です。
個人再生は、裁判所を通じて、借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で計画的に返済していく法的な手続きです。自己破産とは違って全ての財産を手放す必要がなく、特に「住宅ローン付きの自宅(マイホーム)を残したい」と考える人にとって有効な制度です。
今回は、個人再生の基本的な仕組みから、具体的な手続きの流れ、利用するメリット・デメリットまで、企業法務に強い弁護士が解説します。
- 個人再生なら、借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で計画返済できる
- 住宅ローン付きの自宅(マイホーム)が残せる点が最大のメリット
- 個人再生を利用するために、債務額5,000万円以下など厳格な要件がある
\お気軽に問い合わせください/
個人再生とは
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額した上で、原則として3年(最長5年)かけて分割返済する手続きで、民事再生法に定められています。債務者の収入状況を踏まえた再生計画を立て、裁判所の監督の下、計画的に返済します。
個人再生の特徴は、自宅などの財産を残しながら借金を整理できる点です。自己破産にないメリットであり、家族や仕事への影響を最小限に抑えたい方にとって有力な選択肢となります。
個人再生の種類
個人再生には2つの種類があり、状況に応じて選択します。
小規模個人再生
小規模個人再生は、個人再生の種類の中でも一般的な手続きです。
債権者が再生計画に同意することが要件とされますが、給与所得者等再生に比べて弁済すべき債務額が少なくて済むのが特徴です。したがって、個人再生を目指す場合、まずは小規模個人再生から検討します。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、給与など、定期的に安定収入のある人を対象にした個人再生です。
債権者の同意は不要ですが、小規模個人再生よりも返済額が高くなる傾向があります。定期的で、変動幅の少ない収入があることが要件となり、主に会社員や公務員などが利用することができます。
「会社が倒産したときの社長の責任」の解説

自己破産・任意整理との違い
個人再生の特徴を理解するため、他の債務整理の方法(任意整理・自己破産)との違いを比較しておきましょう。
自己破産との違い
自己破産は、法人の資産を換価(処分)して債権者に配当し、支払いきれなかった債務は免責される点が、個人再生との大きな違いです。自己破産だと、借金の返済は全額免除される反面、財産も全て処分しなければなりません。また、自己破産では士業などの一部の資格や職業に制限がありますが、個人再生の場合は制限がありません。
なお、信用情報(いわゆる「ブラックリスト」)に登録され、新たな借入やクレジットカードの作成などができなくなるデメリットは共通です。
任意整理との違い
任意整理は、債権者との交渉によって支払い条件の変更などを行う手続きです。
任意整理も個人再生も、借金を返済する点は共通しますが、任意整理では基本的に、元本分は返済する必要があります(将来リスクのカット、返済期限の猶予などの交渉を行います)。これに対し、個人再生は裁判所を通じ、民事再生法に基づいて手続きを行うことで、借金を大幅に減額できます。
任意再生は、どの債務を整理するか選べるのに対し、個人再生では柔軟に選ぶことはできず、民事再生法に従い、住宅ローンを除くすべての借金を整理します。
「債務整理の種類」の解説

個人再生の要件と対象者
個人再生では、民事再生法の定める要件を満たす必要があります。
個人再生では、裁判所を通じて借金を大幅に減額することができる分、厳格な要件を満たさなければ申し立てができず(個人再生の申立要件)、また、再生計画を認可してもらうことができません(再生計画の認可要件)。
個人再生の申立要件
第一に、個人再生の申立要件を満たさなければ、裁判所に受理されません。
再生開始原因があること
再生開始原因とは、次の事由が該当します。
- 支払不能に陥っていること
- 支払不能に陥るおそれがある状態にあること
- 債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない状態にあること
申立棄却事由がないこと
申立棄却事由とは、個人再生の利用が不適切となる事情のことで、必要な予納金を支払わない場合、収入状況などからして再生計画に従った返済が明らかにできない場合などです。
債務額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること
住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下でなければ、個人再生は利用できません。
個人再生は、自己破産と違って債務が全て免責されるわけではないので、高額過ぎると弁済の継続が難しいと考えられているからです。この際の債務額は、借金や保証債務、外注費やクレジットローンなど、住宅ローンを除く全ての借入が含まれます。
前回の手続きから7年経過していること
給与所得者等再生は、個人再生や自己破産の免責許可決定から7年経過していなければ利用できません。過去に債務整理をしたのに再度借入をした人は厳しく扱われるということです。小規模個人再生なら期間制限はありませんが、裁判所の監督は厳しくなる傾向にありますし、複数回の個人再生の場合には債権者も同意しづらいでしょう。
「自己破産から再起する方法」の解説

再生計画の認可要件
第二に、再生計画の認可要件を満たさなければ、計画認可が得られません。
個人再生を申し立てる時点で、認可要件を満たすような再生計画を立てられるか(返済が可能か)についても検討しておく必要があります。
再生計画不認可の要件がないこと
再生計画の不認可要件は、裁判所が個人再生を認可してはならない類型であり、主に次のものが該当します(民事再生法174条)。
- 再生手続や再生計画に重い法律違反があり、不備の補正ができないとき
- 再生計画が遂行される見込みがないとき
- 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき
- 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき
最低弁済額を上回ること
個人再生には、債務額に応じた最低弁済額が設けられています。この最低弁済額を上回る弁済ができないときは、再生計画の認可が受けられません。
| 債務額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 債務額の全額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円を超え1,500万円以下 | 債務額の5分の1 |
| 1,500万円を超え3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 債務額の10分の1 |
上記の表からも分かる通り、債務額が100万円以下のときは、個人再生を利用しても債務を減額することができません。
債権者の同意が得られること
小規模個人再生では、債権者の同意が、計画認可の要件となります。
この同意は「消極同意」と言われます。具体的には、「不同意かどうか」を確認し、債権者の過半数、債権額の過半数のいずれかが反対の意思を示した場合のみ、計画の認可が受けられなくなります。
特に、取引先や顧客など、個人の債権者がいるケースでは、感情的になって再生計画に反対する可能性があり、事前に同意取得の交渉をしておくべきです。
定期収入の見込みがあること
給与所得者等再生では、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その収入の変動の幅が小さいこと」が要件とされます(申立時、計画認可時のいずれの段階でも検討される)。給与所得者等再生は債権者の同意を要しない分、安定した弁済を確保するためにこの要件があります。
可処分所得の2年分を弁済すること
給与所得者等再生では、最低弁済額に加え、可処分所得の2年分に相当する金額を弁済することが求められます(その結果、小規模個人再生よりも弁済額が高くなる傾向)。
個人再生が向いている人の特徴
以上の要件からして、個人再生は、次のような方に特に適しています。
住宅ローンがあるが家を残したい人
個人再生には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。これを利用すれば住宅ローンの返済を続けながら、他の借金だけを大幅に減額することができます。したがって、家族と住む家(マイホーム)を手放さずに済む点が、自己破産とは異なる点です。
安定収入があるが借金が膨らんでしまった人
本来、収入が十分であれば、借金をする必要はなかったはずです。
しかし、病気や失業、子供の教育費や医療費、親の介護費など、様々な理由で、やむを得ず借金がかさんでしまう人もいます。このとき、今後の安定収入が見込めるのであれば、個人再生を利用して立て直すことができます。
個人再生のメリット・デメリット
次に、個人再生のメリットとデメリットについて解説します。
債務整理の際にどの方法を選択するかは、一長一短であり「正解」はありません。個人再生が適切かどうか、メリット・デメリットを比較して慎重に検討してください。
個人再生のメリット
個人再生の主なメリットは、次の3つです。
借金が大幅に減額される
個人再生のメリットの1つ目は、借金を大幅に減額できることです。
個人再生では、借金の総額に応じて返済額が決められており、最大で5分の1程度にまで減額することができます。例えば、借金が500万円の場合、再生計画が認可されれば100万円程度の返済で済むケースもあります(ただし、最低弁済額はあります)。
減額された借金を3年〜5年で分割返済するという仕組みによって、無理のない範囲での生活再建が可能となる点は、大きなメリットとなるでしょう。
財産(特に住宅)を守りながら債務整理できる
個人再生では、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用することで、持ち家を手放さずに他の借金だけを整理できます。この点は、全財産を処分しなければならない自己破産との最大の違いです。
これにより、生活の基盤を保ちつつ、家族への影響も最小限に抑えることが可能です。
自己破産のような資格制限がない
自己破産の場合、弁護士・税理士・警備員・保険外交員など、一部の資格や職業に制限がかかります(復権すれば回復する)。
これに対し、個人再生には資格や職業の制限はありません。そのため、職場への影響を避けたい会社員や、資格を必要とする専門職にも適した選択肢です。
「法人破産のデメリット」の解説

個人再生のデメリット
個人再生の主なデメリットは、次の3つです。
個人再生は、「家を残したい」「資格を守りたい」という希望が明確な人には非常に有効な制度ですが、信用情報への影響や返済の責任など、デメリットもあります。「それであれば、自己破産しておけばよかった」などとならないよう、慎重に検討してください。
官報に掲載される
個人再生を申し立てた事実は、官報(国の発行する広報紙)に掲載されます。
ただし、官報を日常的に閲覧する一般人はほぼ存在せず、掲載されて周囲に知られるリスクは限定的です。とはいえ、事実として「官報に載る」というデメリットはあり、金融や不動産などの特定の業界では情報が知られる可能性があります。
信用情報(ブラックリスト)に登録される
個人再生を行うと、信用情報機関に登録されます(いわゆる「ブラックリスト」)。これにより、クレジットカードの利用や新たなローン審査が通らなくなる状態が、通常5年〜10年間続きます。
「自己破産をしなければブラックリストには載らないから、個人再生を選びたい」といった誤解が多いので注意してください。
返済計画に沿った支払いが必要
個人再生は、借金が減額されるとはいえ、確実に返済を続ける必要があります。そして、途中で返済が滞ると、再生計画が失効し、元の借金総額に戻ってしまうリスクがあります。民事再生法に基づく法的な手続きなので、任意整理よりも柔軟性は低いです。
したがって、返済期間中は、家計の管理や収支の安定性が強く求められます。
「会社の破産手続きの流れ」の解説

個人再生の手続きの流れ
次に、個人再生を実際に利用する際の、手続きの流れについて解説します。
個人再生は、複雑な裁判手続であり、必要書類も多く存在します。弁護士が代理して進める例が多いですが、全体像を理解しておけばスムーズに進められます。
弁護士に相談する
まず、個人再生に詳しい弁護士に相談します。
個人再生には要件があり、手続きも複雑なので、有効活用するには専門家のサポートが必須でしょう。法律相談では、借金額や収入状況、家計の状態などを整理して、個人再生が適切かどうかをチェックしてもらいます。
正式に依頼すれば、以後の手続きは弁護士が主導して進めてくれるため、精神的な負担を軽減することができます。
受任通知を送付して取立を止める
受任後すぐに、弁護士から各債権者へ受任通知を送付します。
通知後は、債権者が債務者に直接連絡したり、督促や取立をしたりするのは禁止なので、返済も一時的にストップできます。支払いの負担から一旦解放されて、冷静に再建計画を立てる時間を確保します。
家計収支表や財産一覧を整理する
次に、裁判所への申立に備え、家計収支表・財産一覧・債権者一覧などを整理します。個人再生は、法律に基づく厳格な手続きで、安定した返済を継続する必要があるので、事前準備は欠かせません。
正確な情報をもとに、現実的な返済可能額をあらかじめ見極めておきましょう。
個人再生の申立てをする
裁判所に申立書と必要書類を提出し、個人再生手続きの申立てを行います。
裁判所は、申立てを受理した後、個人再生委員を選任します。個人再生委員は、手続きの進行が適切に行われているかを監督する法律専門家であり、弁護士が選任されます(再生債権の評価を要する場合を除き、選任は裁判所の裁量であり選任されない例もありますが、東京地方裁判所では全件選任される運用)。
個人再生手続きの開始決定
申立後、個人再生委員と面談を行い、個人再生の要件を満たすかを確認されます。
裁判所が、個人再生委員の意見を参考にして、個人再生の要件を満たすと判断すれば、再生手続きの開始決定が下されます。
再生計画案を提出する
債務者の収入と生活の状況に基づいて、再生計画案を作成します。
計画には、月々いくら返済するか、何年で完済するかなどを明記して裁判所に提出します。債務額に応じた最低弁済額を守る必要があることと、原則として3年で完済すること(特別な事情がある場合は5年)が必要です。
債権者による同意(小規模個人再生)
小規模個人再生では、提出された再生計画案に対して債権者及び債務額の「不同意」が過半数を越えないことが必要です。具体的には、債権者数の過半数、債権総額の過半数のいずれかが不同意の意思を表明しない限り、再生計画は成立へと進みます。
なお、給与所得者等再生の場合、この同意手続きは不要です。
再生計画の認可決定
小規模個人再生であれば債権者及び債権額の「不同意」が過半数を越えなかった場合、給与所得者等再生であれば同意手続きなく、裁判所が再生計画を認可します。認可決定が下ると、債務が大幅に減額された状態での返済が始まります。
なお、債務者が計画的に弁済できるかを試すため、履行トレーニングが行われることがあります。トレーニング期間に指定された履行を怠ると、計画的な弁済ができないと判断され、個人再生が不認可又は廃止になるおそれがあります。
認可後の返済
再生計画が認可されると、返済が開始されます。
決められた金額を毎月返済し、3年〜5年間の計画に従って支払いが完了すれば、残りの債務を支払う必要はありません。計画通りに弁済されないと、再生計画が取り消されるおそれがあります。
やむを得ない事由がある場合は、再生計画の変更が認められることがあるので、どうしても返済が難しい状況になってしまった場合には早めに弁護士に相談しましょう。
個人再生にかかる費用の目安
個人再生は、裁判所を通じた法的手続きなので、一定の費用がかかります。
個人再生にかかる費用は、主に、裁判所に納付する費用と、申立代理人となる弁護士に依頼するための弁護士費用に分けることができ、それぞれ次の通りです。
裁判所に納付する費用
個人再生において裁判所に納付する費用は、申立手数料(収入印紙代)として1万円程度のほか、予納郵券(郵便切手)が2,000円程度、官報公告費が1万円程度となります。その他に、個人再生委員を選任する場合には、委員の報酬として15万円程度を収める必要があります。
なお、裁判所によって扱いが異なる場合があるので、事前に確認しておいてください。
個人再生の弁護士費用
個人再生の申立てを弁護士に依頼する場合、弁護士費用の相場は30万円〜50万円程度が目安です(債務額や債権者数、業務量などによって増減します)。
多くの法律事務所では、依頼時に発生する着手金と、計画認可時に発生する報酬金を定めます。また、経済的に余裕のない場合、着手金については分割払いが可能で、受任通知を送って返済を止めている間に支払えるよう配慮することが多いです。
初回の法律相談時に、弁護士費用についても無理のない計画で支払えるかどうか、事前に確認しておいてください。
個人再生にかかる期間の目安
個人再生の手続き全体にかかる期間の目安は、次の通りです。
- 弁護士への相談から申立準備まで:1ヶ月〜3ヶ月
- 申立てから認可決定まで:4ヶ月〜6ヶ月
申立てから認可決定までは6ヶ月以内に終わるケースが多く、全体では、6ヶ月〜1年程度を目安として進めていきます。大阪地裁など、一部の裁判所では、申立から認可決定までを100日間のスケジュールで終える「100日ルール」が導入されています。
資料の準備が不十分であったり、生活状況や収入がなかなか安定しなかったり、債権者の対応や個人再生委員の調査に時間がかかったりする場合には、これ以上に長引くケースもあります。
個人再生に関するよくある質問
最後に、個人再生に関するよくある質問に回答しておきます。
個人再生と自己破産で迷う場合は?
個人再生と自己破産はいずれも裁判所を通じた法的な債務整理です。
大きな違いは、自己破産では、借金が全て免除される代わりに財産が処分されるのに対し、個人再生では、借金は大幅に減額されるものの一部は支払わなければならず、一方で財産財産を残すことができる点にあります。
浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合には自己破産はできませんが、個人再生では理由によって認められないことはありません。
個人再生と自己破産の選択の基準は、次のポイントを重視してください。
- 自宅を残したい → 個人再生が有力な選択肢となる。
- 収入が不安定・失業中で無職 → 自己破産が現実的。
- 免責不許可事由がある → 個人再生を選択すべき。
- 財産がほとんどない → 自己破産が選択肢に入る。
判断を誤って後悔しないためにも、迷った場合は、家計や収入、資産の状況を弁護士に見せて、専門的なアドバイスを求めるのが安全です。債務整理について、無料相談で対応してくれる法律事務所も多くあります。
個人再生でクレジットカードはいつまで使える?
個人再生手続きでは、弁護士に依頼した時点で、クレジットカードの利用は実質的に停止するのが基本です。
弁護士が、受任通知を債権者に送付すると、信用情報が記録され、カードは利用できなくなります。再生手続き中や認可後も、いわゆる「ブラックリスト」の状態となり、5年〜10年は新たなカードの作成ができません。
個人再生は家族や職場に知られる?
個人再生手続きが、家族や職場に知られることはありません。
ただし、必ず隠し通せる保証はなく、次の点に注意して行動してください。
- 家計の状況を詳細に出すために、同居家族の収入に関する情報を提出しなければならず、協力が必要なことがある。
- 特に、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を使う場合、家族に関する情報が必要となり、完全に秘密にしておくことが難しいケースもある。
- 裁判所から職場に連絡が入ることはないが、申立前に給与口座を差し押さえされるなど、債権者の行動によっては発覚するリスクがある。
したがって、家族に内緒で進めたい場合、任意整理の方法を選択する場合もあります。なお、個人再生手続きでも、官報に公告されますが、一般人が見ることはほとんどないのが実情です。
まとめ

今回は、個人再生の法律知識について、詳しく解説しました。
個人再生は、借金の返済に苦しむ人が、生活の立て直しを図るために活用できる法的手段です。自己破産のように全ての財産を失わずに済むので、住宅ローン付きの自宅(マイホーム)を守りながら債務整理をしたい人にとって、非常に大きなメリットがあります。
ただし、個人再生は全ての人に適しているわけではありません。借入を大幅に圧縮できる代わりに厳格な要件があり、債務額が5,000万円を超えると利用できません。また、減額されるとはいえ将来返済を続けなければならないので、安定した収入も必要です。
借金問題を抱えている方は、一人で悩まず、弁護士に相談してください。個人再生をはじめ、債務整理の方法があなたにとって最適な選択肢かどうか、アドバイスします。
- 個人再生なら、借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で計画返済できる
- 住宅ローン付きの自宅(マイホーム)が残せる点が最大のメリット
- 個人再生を利用するために、債務額5,000万円以下など厳格な要件がある
\お気軽に問い合わせください/